 cortisちゃん
cortisちゃん最近、朝起きるのが本当にしんどくて…。何時間寝てもだるさが抜けないんです。
 日原 裕太
日原 裕太それ、自律神経の乱れが原因かもしれませんよ!
今日は、朝の目覚めが変わる習慣を5つご紹介しますね!
この記事で分かること
- 朝のだるさの原因と自律神経との関係
- 寝起きを改善する5つの習慣
- 睡眠の質を高める環境づくりのコツ
- 自律神経を整えて毎朝スッキリ目覚める方法
朝のだるさの原因は?自律神経の役割を解説
朝起きたときにだるいと感じる大きな要因は、自律神経(交感神経・副交感神経)の切り替え不良と体内時計のズレです。夜にしっかり休むための“副交感神経優位”から、朝に活動するための“交感神経優位”へスムーズに切り替わらないと、目覚めが悪くなります。生活習慣を整えることで、目覚めは改善しやすく、快眠にもつながります。
自律神経とは何か
自律神経は、私たちの意思とは関係なく体の働きを調整する神経です。
心拍や体温、血圧など無意識に体のバランスを調整しています。
詳しくは、第一三共ヘルスケアの 「“自律神経”の重要な働きとは? ストレスや加齢との関係も解説」をご覧ください。
- 交感神経:活動モード。心拍・血圧・体温を上げ、日中のパフォーマンスを支えます。
- 副交感神経:休息モード。消化を促し、入眠や回復を助けます。
理想的な1日の流れは、夜は副交感神経が優位→朝は交感神経が自然に高まること。朝にこの切り替えがうまくいかないと、起きたのにボーッとする、体が重いといった朝のだるさが出やすくなります。
※健康状態に不安がある・だるさが長引く場合は医療機関の受診を検討してください。
自律神経が乱れる主な生活習慣
次のような要因は、自律神経のリズムや体内時計を乱し、目覚めを悪くします。
- 就寝前のスマホ・PC:強い光(特にブルーライト)は体内時計を後ろにずらし、入眠を遅らせます。
- 不規則な就寝・起床/“寝だめ”:毎日の時刻がズレると、脳の時計が安定せず朝に交感神経が上がりにくい。
- 夜のカフェイン・寝酒:カフェインは覚醒を引き延ばし、アルコールは睡眠の質(深さ)を下げます。
- 朝の光不足・夜の強い光:朝の自然光は体内時計を“朝モード”に合わせる合図。浴びないと切り替えが遅れます。
- 運動不足・日中座りっぱなし:日中の適度な活動は、夜の副交感神経優位を後押し。不足でリズムが乱れがち。
- 寝室環境の不備(暑い/寒い・騒音・寝具不適合):眠りが浅くなり、回復が不十分に。
- ストレス過多・寝る直前の作業やSNS:交感神経が高ぶり、入眠や回復を妨げます。
- 朝だるい ⇢ 自律神経の切り替え不良+体内時計のズレが背景になりやすい
- 光・時刻・刺激(カフェイン/スマホ)・活動量・環境を整えるのが第一歩
- 小さな習慣の見直しで、目覚めの質は上げられる
 cortisちゃん
cortisちゃん朝にスイッチが入らない感じがずっと続いてて…
 日原 裕太
日原 裕太まずは光・時刻・刺激の3点を整えましょう。切り替えがスムーズになりますよ!
睡眠の質を上げる3つのポイント
睡眠の質を高めるには、光の管理・環境の最適化・習慣の見直しが重要です。これらを整えることで深い眠りが促され、翌朝の目覚めも軽くなります。
スマホ・照明コントロールで深い睡眠へ
就寝前1〜2時間はスマホやPCの強い光(ブルーライト)を避けることが大切です。ブルーライトは脳を覚醒させ、体内時計を遅らせてしまいます。照明は暖色系の柔らかい光に切り替えるのが効果的。間接照明や調光ライトがおすすめです。どうしてもスマホを見る場合は、ナイトモードやブルーライトカット機能を活用しましょう。
快眠を促す寝室環境の整え方
室温は夏26℃前後/冬18〜20℃が目安。湿度は50〜60%に保つと快適です。寝具は季節や体質に合ったものを選びましょう。敷布団・マットレスの硬さは、体が沈み込みすぎない程度が理想です。遮光カーテンや耳栓などで光・音の刺激を減らすと、眠りの深さが安定します。アロマやリラックス音楽など、副交感神経を優位にする刺激を取り入れるのも◎。
寝室は静かで暗く、適切な温度・湿度を保つことが重要です。
- 光の管理:夜はブルーライトを避け、暖色照明でリラックス
- 環境の最適化:室温・湿度・寝具を整えて快眠へ
- 刺激のコントロール:光・音を減らし、入眠スイッチを入れる

朝のだるさを解消する習慣5選
深呼吸&軽いストレッチ
朝一番でゆっくりと深呼吸をすることで副交感神経から交感神経への切り替えが促され、首・肩・背中を軽く回したり前屈や伸びをするストレッチで血流が促進されて体温が上がります。
コップ一杯の水で内臓スイッチON
起床後に常温水か白湯を飲むことで就寝中に失った水分を補給し、血液をさらさらにして腸のぜん動運動を促し、排便リズムを整えます。
朝食に取り入れたい栄養素
朝食には卵や納豆、ヨーグルトなどのたんぱく質、豚肉や玄米などのビタミンB群、ご飯や全粒パンなどの糖質をバランスよく取り入れることで活動エネルギーと代謝を高められます。
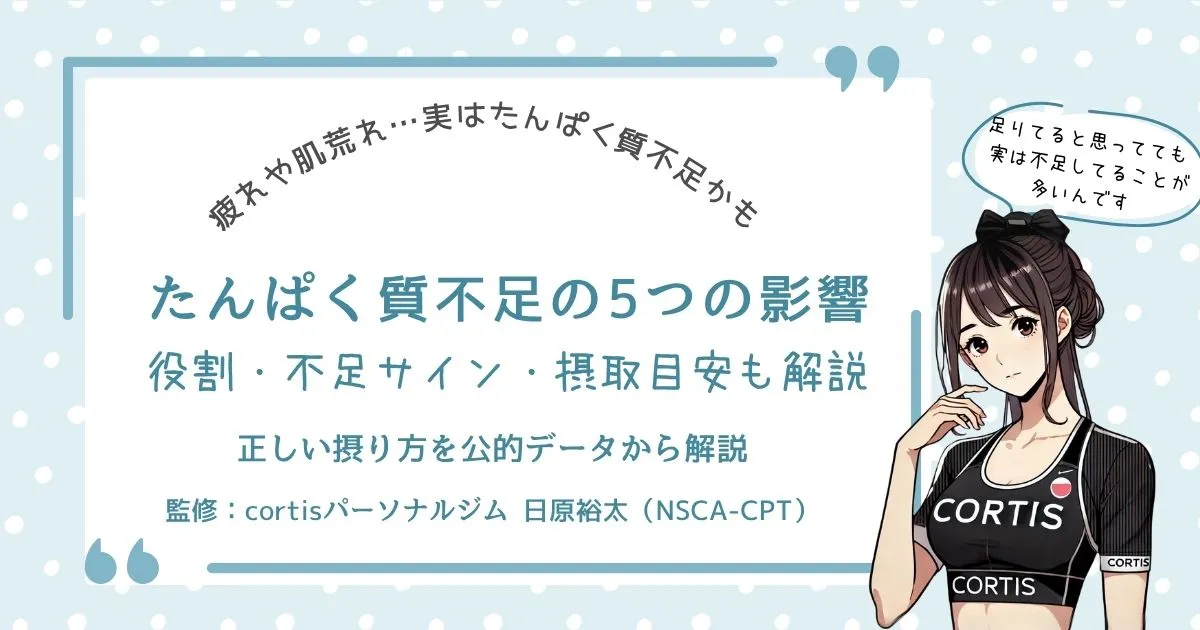
朝日を浴びるベストタイミング
起床後30分以内に自然光を浴びると体内時計がリセットされ、夜のメラトニン分泌リズムが整い、天気が悪い日でも窓際で光を浴びるだけで効果があります。
血流を促す立ち&ウォーキング習慣
朝の軽い運動は交感神経を高めて代謝を上げるため、通勤時に一駅分歩いたり家事を立ったままするだけでも効果があり、無理のない範囲で毎朝少しずつ続けることが重要です。
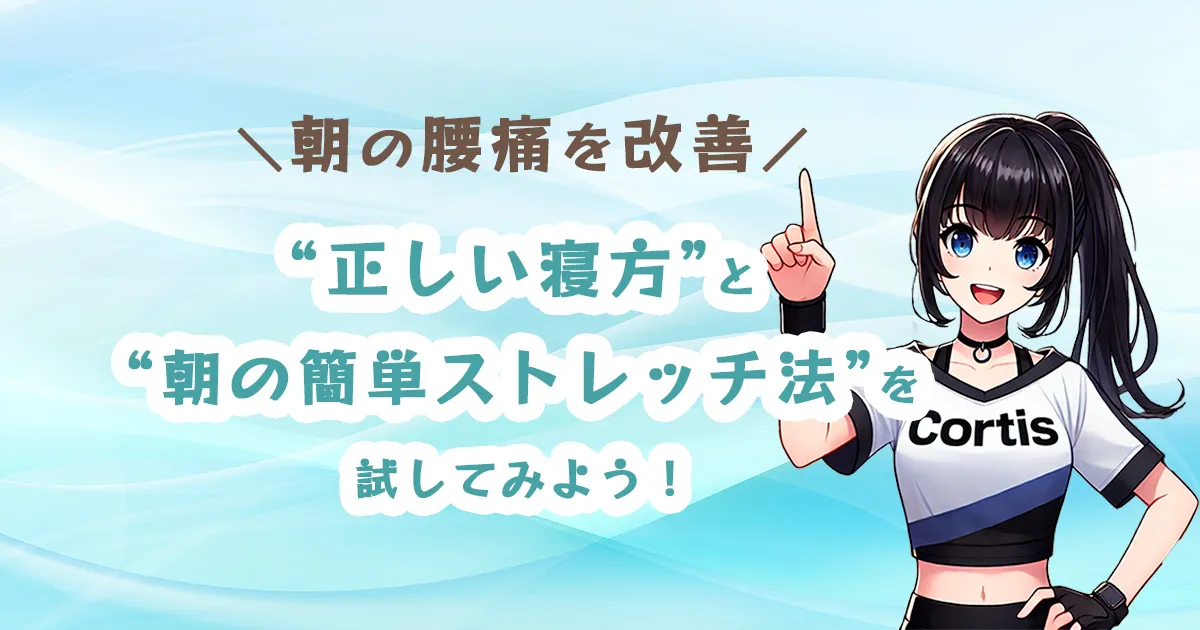
目覚めをサポートする光目覚まし時計を活用する
日の出を再現する光で自然な覚醒を促す光目覚まし時計は特に冬や曇りの日など朝日が浴びにくい環境で効果的で、習慣化することで朝のスイッチが入りやすくなります。
光目覚まし時計・10000lux UVフリーフォーム(日の出シミュレーション機能付き)
- 深呼吸&ストレッチで血流・体温を上げる
- 朝の水分補給で内臓と腸の動きを促す
- バランス朝食で活動エネルギーと代謝を上げる
- 朝日を浴びて体内時計をリセット
- 軽い運動で交感神経を高める
- 光目覚まし時計で朝スイッチをサポート
生活リズムを整える見直しポイント
就寝・起床時間の固定と効果
毎日ほぼ同じ時間に寝て同じ時間に起きることで体内時計が安定し、自律神経の切り替えがスムーズになって朝の目覚めが軽くなります。
寝だめがもたらす逆効果
休日の寝だめは一時的な睡眠不足の解消にはなりますが体内時計を乱しやすく、翌日の起床がつらくなる原因になります。
詳細は厚生労働省「昼間の眠気 – 睡眠・覚醒障害にも注意を」をご覧ください。
- 就寝・起床時間を一定にして体内時計を安定させる
- 寝だめは体内時計を乱し、逆効果になることがある
まとめ:自律神経を整えてすっきり目覚める
毎日続けたい3つの習慣
朝に光を浴びる、コップ一杯の水を飲む、軽いストレッチを行う、この3つを日課にすることで自律神経の切り替えがスムーズになり、だるさのない目覚めが期待できます。
自分の体調をチェックする方法
朝のだるさや日中の眠気が続く場合は生活リズムの乱れや睡眠の質の低下が原因かもしれないため、日々の行動や睡眠時間を記録して傾向を把握し、必要に応じて改善や医療機関の相談を行いましょう。
- 光・水・ストレッチの3習慣で目覚めを改善
- 不調が続く場合は行動記録で原因を探り、早めに対策

コメント