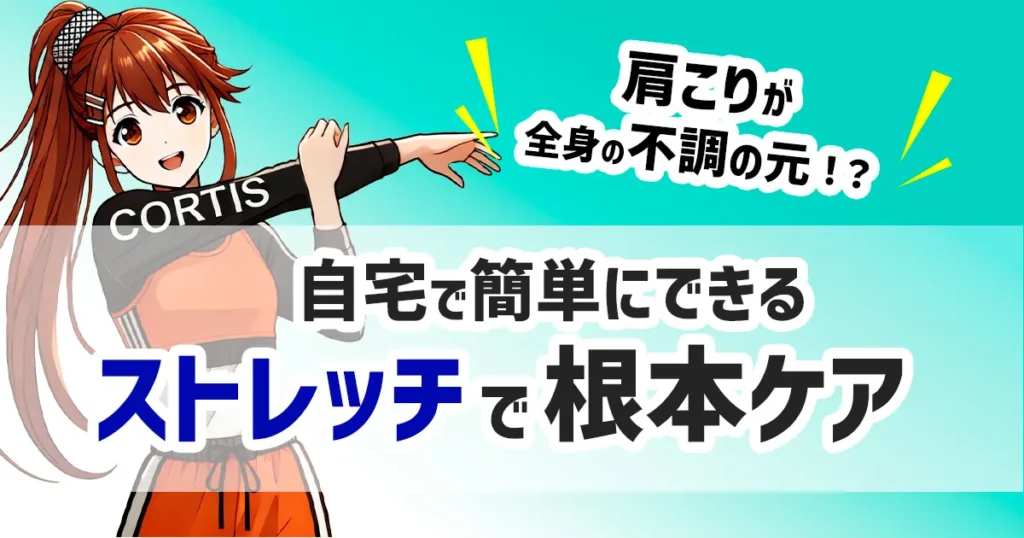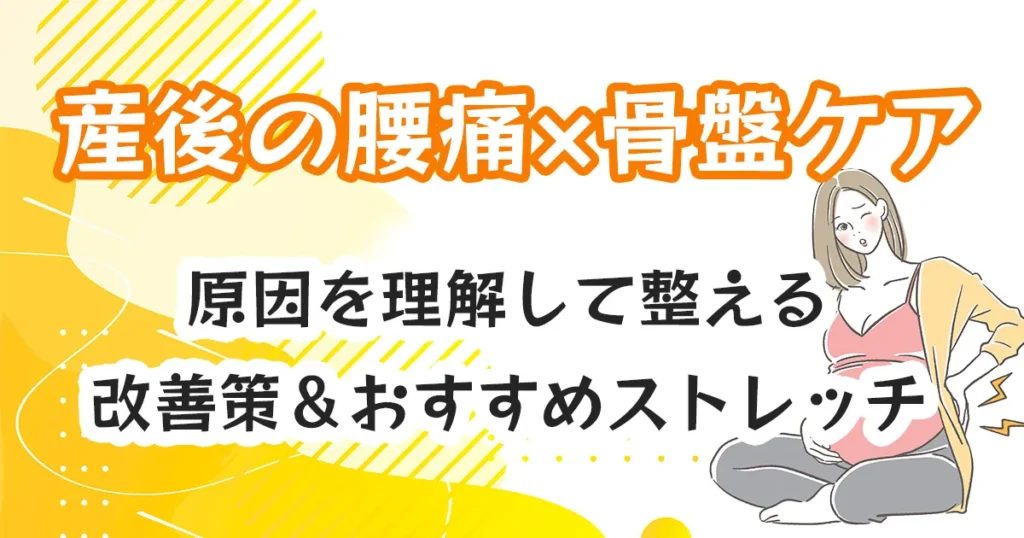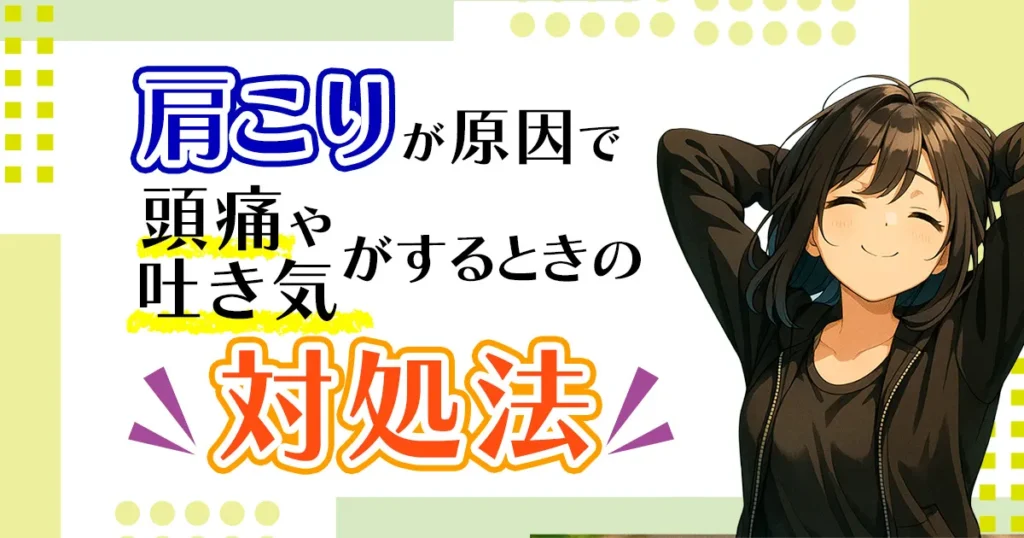追記:この記事を曲にして分かりやすくまとめました。
※本記事は、cortisジム代表・日原裕太が、実際に「肩こり本」Kindle出版&現場での改善指導を多数実施してきた実体験をもとに執筆しています。
書籍はコチラ!
 cortisちゃん
cortisちゃんんにちは!cortisパーソナルジムです。
今日は、頭がズーンと重い、肩がガチガチにこる…そんなお悩みを抱えているあなたに向けて、“原因から対策まで”が1記事でわかるセルフケア解説をお届けします!
 日原 裕太
日原 裕太大丈夫。
ちゃんと原因を知って、今日からできるケアを始めよう。
この記事でわかること
- 肩こりや頭痛が起こる主な原因とは?
- 自宅でできるリラクゼーション習慣5選(ストレッチ・呼吸法など)
- リラクゼーションテクニックの正しい実践方法
- 毎日のセルフケアを継続するためのコツ
- 専門家のサポートが必要な場合の見極め方
【肩こり・頭痛の原因】今すぐ見直したい3つの生活習慣
現代人の多くが悩まされる、慢性的な肩こりや頭痛。
その大きな原因は、「ストレス・姿勢・血行不良」の3つにあります。
どれも日常の“クセ”や“環境”から来るものなので、まずは自分の生活を見直してみましょう。
① ストレスが原因で自律神経が乱れると、肩こりや頭痛につながる
仕事や人間関係など、日々のストレスが溜まってくると、私たちの体は「交感神経」が優位になりやすくなります。
これは、常に緊張モードで戦っているような状態。
その結果、筋肉はこわばり、血管は収縮し、血流が悪化して首・肩のこりや頭痛の原因になります。
特に「緊張型頭痛」と呼ばれるタイプは、このストレス状態と深く関係しています。
 cortisちゃん
cortisちゃんまずは「自分は今、緊張していないか?」に気づくことが、セルフケアの第一歩です!
② 長時間の同じ姿勢は、血行を悪くし肩こり・頭痛の元に
パソコン作業やスマホ操作など、長時間同じ姿勢を続けることで、肩・首の筋肉に大きな負担がかかります。
特に猫背やストレートネックの姿勢は、首から肩にかけて筋肉を緊張させ、血流を滞らせやすいのです。
血行が悪くなると、酸素や栄養が行き届かず、筋肉疲労や老廃物の蓄積が起こります。
これが肩こりや頭痛、だるさの原因となるのです。
 cortisちゃん
cortisちゃん冷房や冬場の寒さも血流を妨げるため、こまめな体温管理とストレッチが効果的です。
③ 姿勢のクセが筋肉を固め、慢性的な不調に
私たちの身体は、正しい姿勢を保っているときにもっとも楽な状態です。
しかし、無意識にしている「首を前に突き出す」「片方に体重をかける」などの悪い姿勢のクセが、筋肉の緊張を慢性化させてしまいます。
この状態が続くと、脳が“こり状態”を普通だと誤認し、リラックスしづらくなる傾向も…。
これが慢性的な肩こりや頭痛を引き起こす負のループです。
 cortisちゃん
cortisちゃんまずは「自分の姿勢の癖」に気づくことから。改善はそこから始まります。
【あなたの頭痛タイプは?】3つの症状を見分けて、最適な対策を


一口に「頭痛」や「肩こり」といっても、その原因や現れ方は人それぞれです。
自分の症状タイプを理解することで、より効果的なセルフケアが選べるようになります。
ここでは、よく見られる代表的な3つのタイプをご紹介します。
緊張型頭痛とは?
もっとも一般的な頭痛で、「頭全体が締め付けられるような鈍い痛み」が特徴です。
ストレス・疲労・長時間の同じ姿勢などで、首や肩まわりの筋肉が緊張して発症します。
- 痛みは軽度〜中等度、頭の両側に広がるような感覚
- 朝よりも夕方に悪化しやすい
- 吐き気や光・音への過敏は少なめ
- 安静にしても大きな改善が見られないことも
リラクゼーションやストレッチで筋肉のこわばりを和らげることで、症状の緩和が期待できます。
 cortisちゃん
cortisちゃん「最近、頭が重い」「肩や首が張ってきたあとに痛くなる」
そんな方は緊張型頭痛の可能性が高いかもしれません。
【放置すると危険?】肩こりが引き起こす4つの関連症状
「ただの肩こり」と思っていると、実は全身の不調につながることがあります。
特に血流や神経の滞りが引き金となり、以下のような症状が現れることも。
頭痛
肩や首の筋肉が緊張し、血流が悪くなることで、酸素不足→頭痛発生のパターンに。
眼精疲労・視界のかすみ
首まわりの血行不良は、目の筋肉や視神経にも影響。
目の疲れ・ぼやけ・ピントが合わない感覚などにつながることも。
めまい・ふらつき
首の後ろ側(後頭下筋群)が強くこると、自律神経のバランスが乱れ、立ちくらみやめまいが起きやすくなります。
集中力の低下・睡眠の質の悪化
肩こりによる不快感が続くことで、集中力が落ちたり、入眠困難・中途覚醒・眠りの浅さといった睡眠の不調も引き起こします。
 cortisちゃん
cortisちゃん肩こりは全身に波及する“警告サイン”。放置せず早めのケアを。
【根本改善のカギは】予防とセルフケアの“習慣化”
頭痛や肩こりは、日々の生活習慣に根本原因があるケースが多数です。
- 痛くなったら湿布を貼る
- 辛くなったらマッサージに行く
こうした対処療法も必要ですが、それだけでは再発を防げません。
予防のための“ちょっとした習慣”が効果的
- こまめに肩を回す
- 深呼吸でリラックスする
- 姿勢の崩れに気づいたらすぐ修正
- 毎日1分の首ストレッチ
など、小さな積み重ねが「コリにくい体質づくり」につながります。
自分のクセを“知って”ケアする
- 「私は緊張しやすい」
- 「つい肩に力が入っている」
そんな自分の傾向に気づくだけでも、体は変わり始めます。
毎日の中にリラクゼーションを“習慣”として組み込むことが、不調改善の近道です。
 cortisちゃん
cortisちゃんまずは「自分は今、緊張していないか?」って、ちょっと立ち止まってみるのがセルフケアの第一歩だよ!
自宅でできるリラクゼーション習慣5選


ゆっくり深呼吸で心身を整える
静かな場所で、リラックスできる体勢をとりましょう。
ヨガの「シャヴァーサナ(仰向けの脱力姿勢)」のように、背中を床につけて横になるのもおすすめです。
両手のうち片方をお腹に、もう片方を胸に軽く添えます。
これから行う呼吸で、お腹・胸・鎖骨の順に空気が流れていくのを感じながら、深くゆっくりと呼吸していきましょう。
【呼吸のステップ】
- 鼻からゆっくりと息を吸い込みます。
→ お腹 → 胸 → 鎖骨の順に空気が入っていくイメージです。 - 吐くときも同じように、
→ 鎖骨 → 胸 → お腹の順に空気を外へ送り出します。 - 呼吸のリズムに合わせて、ゆっくり5回ほど繰り返しましょう。
慣れてきたら、音楽を流しながらリズムに合わせて呼吸を整えるのもおすすめです。
深く吸って、ゆっくりと吐くことで、心拍数が落ち着き、全身が自然とリラックス状態へと導かれます。
最後は手を下ろして、自然な呼吸に戻しましょう。
そのまま仰向けでしばらく“静けさ”に身をゆだねても良いですし、起き上がるときは両膝を立て、身体を右側に転がすようにして、ゆっくりと起き上がるようにすると負担がかかりません。
ワンポイント
深呼吸は、心と身体の“再起動ボタン”のような存在です。
1日数分、静かに呼吸と向き合う時間を持つだけで、自律神経のバランスが整い、肩こりや頭痛の予防・緩和にもつながります。
↓参考動画はコチラ↓
筋肉をゆるめてリラックス!やさしい筋弛緩法(プログレッシブ・リラクセーション)
肩こりや頭痛の原因の一つに、無意識の「筋肉のこわばり」があります。
日常生活の中で緊張やストレスが続くと、身体は常に“構えた状態”になり、筋肉が固まってしまいます。
プログレッシブ・リラクセーション(正式には「プログレッシブ・マッスル・リラクセーション」)は、筋肉を一度ぎゅっと緊張させ、その後ストンとゆるめるという動作を繰り返すことで、身体全体をリラックス状態へ導く手法です。
実践の流れ(座ったままでもOK)
- 静かな場所で楽に座り、背筋を伸ばします。
- まずは呼吸に意識を向け、ゆったりとしたリズムで深呼吸を。
- 足先から順に、各部位の筋肉にやさしく力を入れたあとに脱力。
(例:つま先を上げて5秒→力を抜いて10秒) - ふくらはぎ、太もも、手、腕、肩、顔…と、上へ向かって全身をほぐします。
力を入れるときは「少し頑張る」くらい、抜くときは「全部手放す」イメージで行うのがポイントです。
このような筋弛緩の動作を続けることで、自律神経のバランスが整い、血流も良くなります。
終わったあとは、身体がじんわり温まり、心まで穏やかになるのを感じるでしょう。
🌿POINT
ストレスを感じたとき、寝る前、仕事の合間など、ほんの数分でもOK。
「力を入れて、抜く」というシンプルな習慣が、心と身体のリセットに役立ちます。
↓参考動画はこちら↓
心を落ち着ける瞑想・マインドフルネス
忙しい日々の中で、知らず知らずのうちに心も身体も緊張していませんか?
そんなときこそおすすめなのが、「マインドフルネス瞑想」です。
今この瞬間の呼吸や感覚に意識を向けることで、頭の中のノイズが静まり、心に余白が生まれます。
今回ご紹介するのは、初心者でも安心して実践できる思いやりの瞑想。
日々頑張っている自分自身に、優しさと感謝の気持ちを向けることがテーマです。
瞑想の流れ(抜粋)
- 静かに座り、骨盤を安定させて背筋を伸ばします。
- 鼻からの呼吸を感じながら、「吸っていること」「吐いていること」に意識を向けていきます。
- 手をハートの辺りに添えたり、自分自身をやさしく抱きしめるような姿勢をとってみましょう。
- 心の中で、こんな言葉を繰り返します:
>「私が幸せでありますように」
>「私の悩み・苦しみがなくなりますように」
>「私の夢や願いが叶いますように」
そして、自分自身が今かけてほしい言葉を、そっと届けてあげましょう。
「いつもありがとう」「頑張ってるね」「愛してるよ」——
その言葉が、身体中にじんわりと広がっていくのを感じながら、しばらく深呼吸を続けます。
瞑想が終わったあとは、ほんの少し心が穏やかになっているはずです。
たった数分でも、自分を思いやる時間を持つことが、心身の回復と安定につながります。
継続することで、その効果はより深く、日常の中に広がっていきます。
↓参考動画はこちら↓
肩・首をゆるめる簡単ストレッチ
~正しい姿勢を支える「頚長筋」を目覚めさせよう~
現代人に多い肩こりの原因のひとつが、「頚長筋(けいちょうきん)」という首のインナーマッスルがうまく使えていないことです。
頚長筋は、首の前側、頸椎に沿ってついている深層筋で、本来は頭を支え、自然な姿勢を保つ役割を担っています。
この筋肉が弱まっていると、頭の重みを支えきれず、あごが前に出た“ストレートネック”のような姿勢になり、結果として首や肩の後ろ側に過剰な負担がかかってしまうのです。
頚長筋を目覚めさせる!簡単エクササイズ(寝たままでOK)
- 仰向けに寝て、両腕をまっすぐ天井に伸ばします。
- あごをしっかり引き、首の後ろの空間を軽くつぶすイメージでセット。
- 頭頂部を持ち上げる意識で、首を丸めながら肩甲骨の下まで身体をゆっくり持ち上げ、3秒キープ。
- そのまま、あごを引いたままゆっくりと頭を戻します。
これを1日3回繰り返すことで、頚長筋が目覚め、姿勢の安定に繋がります。
肩甲骨の動きを加えた応用ストレッチ
- 両腕を天井に向けてまっすぐ伸ばした状態から、手のひらを外側に向けます。
- 肘を後方に引きながら、肩甲骨を内側へ寄せるように意識して動かしましょう。
- 呼吸を止めず、無理のない範囲で5~6回を目安に行ってください。
この2つのストレッチは、肩・首の可動域を広げ、筋肉のバランスを整える効果があります。
継続することで、頚長筋が自然に働き、肩こりの根本改善にもつながります。
↓参考動画はこちら↓
セルフマッサージで血流を促進する
~正しい頭の位置が肩こり改善のカギ~
首や肩のこりを根本から改善するには、「頭の位置」を正しいポジションに戻すことが大切です。
そのためには、首の後ろだけでなく、前側や横側の筋肉をやさしく緩めるセルフケアがとても効果的です。
首まわりをやわらかく整えるステップ
- 斜角筋(首の横の筋肉)をほぐすストレッチ
・背筋を伸ばし、右手を左の側頭部に添えます。
・手の重みで、ゆっくりと頭を右に倒し、左側の首筋を伸ばします。
・反対側も同様に行いましょう。 - 斜め後ろの筋肉をターゲットに
・頭を斜め前に倒すことで、首のやや後方の筋肉も効果的に伸ばせます。
・それぞれ2〜3回ずつを目安に。 - 首の前側(胸鎖乳突筋・広頚筋)をストレッチ
・親指を鎖骨の上に添え、口を閉じたまま、あごを少し突き出すように上を向きます。
・余裕がある方は、あごを斜めに傾けることで、左右の前側筋がより伸びます。 - 頸椎の調整ストレッチ
・両手の指を後頭部寄りの首の両側に軽く添え、前方にやや圧をかけながら、ゆっくりと上を向いていきます。
・この動作を3〜5回ほど繰り返します。
※無理に真上を向こうとせず、心地よい範囲で行いましょう。
こうしたセルフケアを取り入れることで、首の可動域が広がり、血流の改善や肩こりの緩和につながります。
特にデスクワークやスマホ使用が多い方には、日常的なメンテナンスとしておすすめです。
↓参考動画はこちら↓
リラクゼーション習慣を続けるためのコツ


日常生活にリラクゼーションを“無理なく取り入れている”イメージを視覚的に伝える図解風イラスト。
スケジュール管理や自分の時間を持つことの大切さを象徴します。
習慣化には「時間と場所のルール化」が効果的
リラクゼーションを習慣にするためには、「いつ・どこで行うか」をあらかじめ決めておくことがとても有効です。
たとえば――
- 朝のコーヒー前に3分間の深呼吸をする
- 夜寝る前、ベッドに入る前に首のストレッチを行う
- 仕事の休憩時間に、椅子に座ったまま肩を回す
といったように、既にある日常の行動と組み合わせて「場所」と「時間」を固定することで、自然とリラクゼーションが生活の一部になっていきます。
「気が向いたときにやる」ではなく、「毎朝◯時に」「お風呂のあとに」とルールを定めておくと、継続のハードルがぐんと下がります。
 cortisちゃん
cortisちゃん糖質制限ダイエットはよく聞きますが、完璧に抜くのはNGです。せっかく筋肉をつけようとしているのにエネルギー不足になると筋肉を分解してエネルギーに変えてしまうので非効率的ですよね。
糖質も脂質もダイエットの敵に見えてしまうかもしれませんが、適量を守って効率よく美ボディを手に入れましょう!
忙しい人ほど“立ち止まる時間”をつくろう
「時間がないからこそ、リラックスする余裕なんてない」——
そう思う方こそ、実は“意識して立ち止まる時間”が必要です。
仕事や家事、育児、移動……やることに追われ続ける毎日は、知らず知らずのうちに呼吸が浅くなり、思考も身体も緊張状態に。
だからこそ、たった1分でも「何もしない時間」をつくることが、自律神経の回復やメンタルの安定につながります。
たとえば…
- トイレ休憩のついでに、目を閉じて3回深呼吸
- エレベーターを待つ時間に、肩を軽く回してリセット
- 帰宅後すぐ、靴を脱いだ瞬間に一度立ち止まって大きく息を吐く
ほんの小さな“立ち止まり”が、日々の疲れを流し、前向きなエネルギーを取り戻すための第一歩です。
こんなときは専門家に相談を
セルフケアやリラクゼーションを続けても、
「なかなか症状が改善しない」「痛みや不調がむしろ強くなってきた」
という場合は、無理をせず専門家のサポートを受けることも大切です。
特に次のようなケースでは、早めの相談をおすすめします。
- 肩こりや頭痛が慢性的に続き、日常生活に支障が出ている
- マッサージやストレッチでかえって痛みが悪化した
- 手足のしびれやめまい、吐き気などの症状を伴う
- 姿勢の崩れや骨格の歪みが気になる
プロのトレーナーや整体師、理学療法士などの専門家は、個々の体の状態に合わせた適切なケア方法を提案してくれます。
セルフケアは「自分を大切にする入り口」。
より良い状態を目指すためにも、ときには“頼ること”も前向きな選択肢です。
 cortisちゃん
cortisちゃんトレーニングの効果は個人差があるので、中々結果が出てこないと心配になったり、諦めたくなっちゃいますよね。でも継続こそ力なりです!パーソナルトレーニングジムでは個々のお悩みに合わせてトレーニング内容等ご提案していますので、「自分なりに調べながら頑張ってきたけど…何やってもダメだった…」という方は一度パーソナルトレーニングジムに相談してみてもいいかもしれませんね!
「セルフケアでは限界があるかも…」そう感じたあなたへ
もし、「セルフケアを試してみたけれど、なかなか改善しない…」
「もっと自分の体に合ったケアを受けたい」
そんな思いがある方は、一度プロの目線で身体をチェックしてみませんか?
cortisパーソナルジムでは、肩こり・頭痛・猫背などのお悩みに対して、姿勢・筋肉バランス・生活習慣を総合的に分析し、オーダーメイドの改善プログラムをご提案しています。
📩 LINE登録で限定特典をプレゼント中!
今なら、LINEご登録で以下のような特典がもらえます!
🎁『333入浴法マニュアル』
🎁『セルフケアチェックリスト』
🎁 サウナで健康作りするための本(電子書籍)
を無料配布しております♪
 cortisちゃん
cortisちゃん登録後に「333」と送ってみてください♪

🏋️ cortisパーソナルジムの特別体験も受付中!
肩こりや頭痛、姿勢のお悩み、またはボディメイクに挑戦したい方、プロと一緒に根本からケアしてみませんか?
🔹 オンライン無料カウンセリング:0円
🔹 トレーニング体験セッション:1,500円(税込)
※全国どこでもオンラインOK、横浜エリアも対応可能です!
もし、対面での体験が不安な方には、30分のオンライン無料カウンセリングもご用意しています!
✅ 今、注目のセルフケア本【3選】
すべて、パーソナルジムcortis代表・日原裕太による執筆。
心と身体、そして習慣づくりの視点から、現場経験をもとにした実践的なセルフケア術をまとめています。