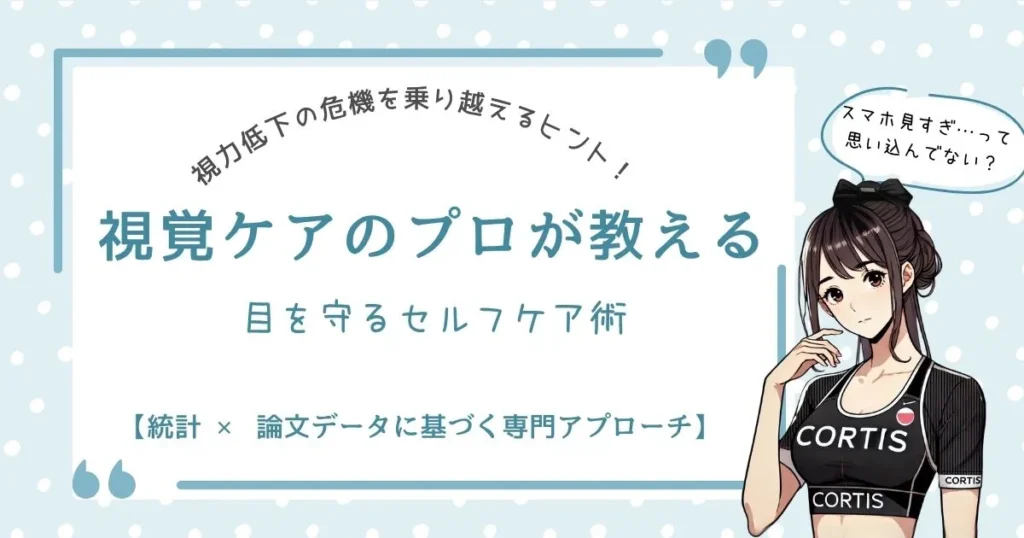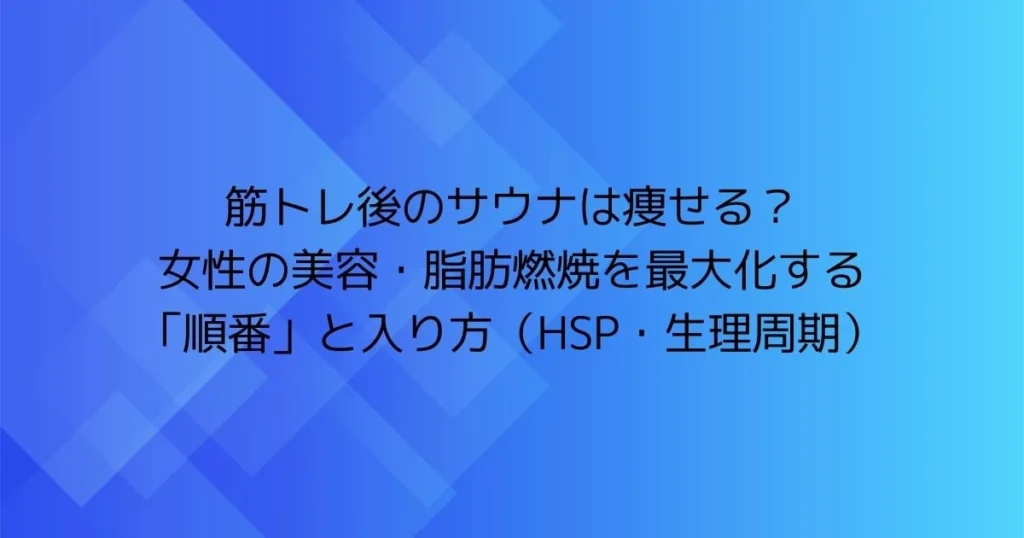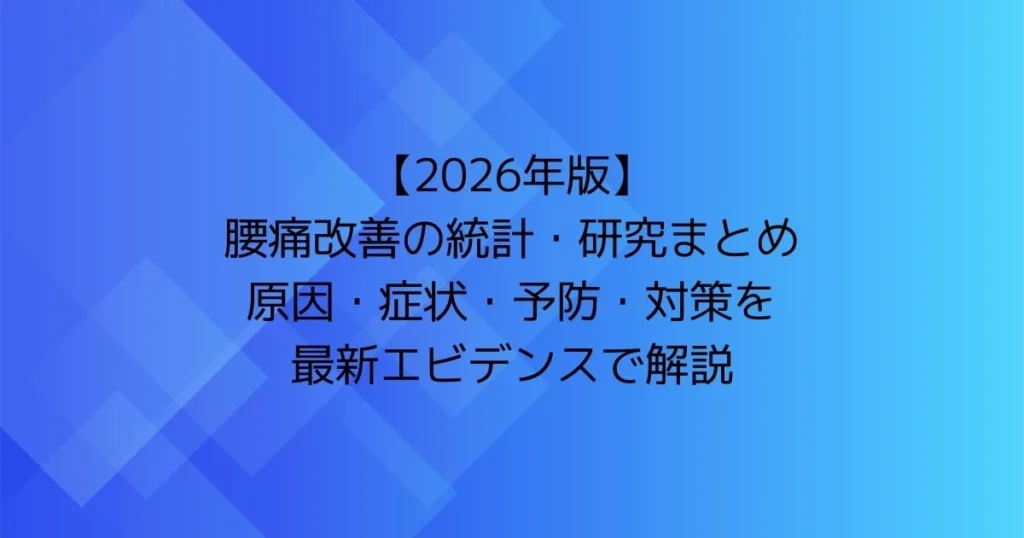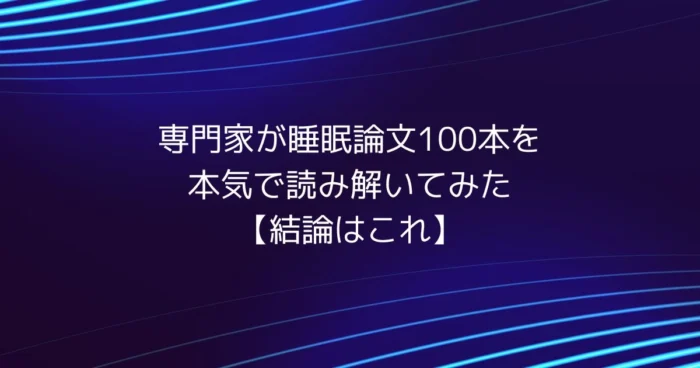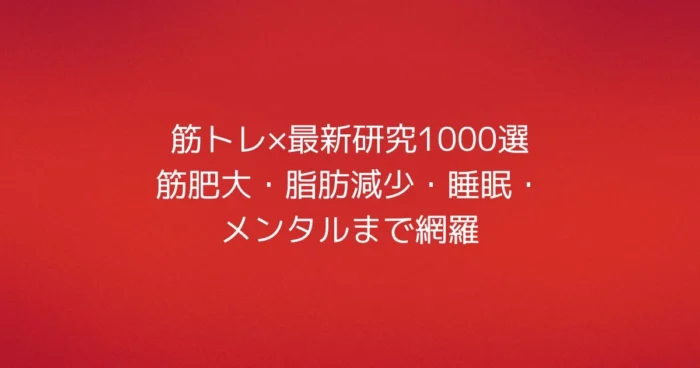追記:こちらのブログ記事を分かりやすく歌でまとめました。
※本記事は、cortis出版代表・日原裕太が、教育現場やフィットネス業界、そして健康・医療領域の情報発信支援を通じて得た実践知と、論文・公的統計データに基づいて執筆しています。
この記事では、
- なぜ子どもの近視が急増しているのか
- ブルーライトやスマホが視力に与える影響
- ドライアイ・眼精疲労・高齢者の眼疾患の実態
- 年代別の眼鏡・コンタクト使用率や今後の予測
について、2025年の最新統計と研究をもとに、誰でも理解できるように整理しています。
 cortisちゃん
cortisちゃん最近、目の疲れがひどくて…。
子どもの視力もどんどん落ちていて心配です。
 日原 裕太
日原 裕太実はその不安、統計でも明らかになっています。
裸眼視力1.0未満の子どもはすでに約7割にのぼり、高齢者の目の疾患も増加傾向にあります。
本記事では、そうした最新の研究や実態を詳しくまとめました。
目の健康や生活習慣に不安のある方へ。
下記ボタンより、cortisパーソナルジムの公式LINEを追加いただけます。

視力に関する日本の最新統計(2025年版)
本節では、最新の全国調査データをもとに、日本人の視力状況を概観します。学校健診データや高齢者の疾患率など、多角的に「見える」現状を把握し、今後の対策や注目ポイントを整理します。
 cortisちゃん
cortisちゃん「みんなの“視る力”は年齢や環境でこんなに変わるんだね!これから深掘りしていくよ。」
裸眼視力1.0未満の割合(小中高生のデータ)
文部科学省「令和6年度学校保健統計調査」では、小・中・高それぞれの児童生徒における裸眼視力1.0未満の割合が過去最高水準となりました。具体的には、小学生で約30%、中学生で約60%、高校生では約70%に達しています。
| 学校種別 | 裸眼視力1.0未満の割合 |
|---|---|
| 小学生 | 約30% |
| 中学生 | 約60% |
| 高校生 | 約70% |
高齢者の視力低下と疾患率
加齢に伴い、緑内障や白内障などの疾患は急増します。40歳以上では約5%が緑内障、60歳代では約75%が白内障に罹患するとされ、日本の高齢視覚健康の大きな課題となっています。
40歳以上の成人では20人に1人が緑内障である。
白内障は50歳代で45%、60歳代で75%、70歳代で85%、80歳以上で100%に達する疾患である。
| 疾患名 | 年齢 | 有病率 |
|---|---|---|
| 緑内障 | 40歳以上 | 約5% |
| 白内障 | 60歳代 | 約75% |
| 白内障 | 70歳代 | 約85% |
| 白内障 | 80歳以上 | ほぼ100% |
引用元:日本緑内障学会「沿革‐データ解析」、済生会横浜市南部病院「白内障の発症率」
近視の進行と世界的な「視力パンデミック」
本節では、近視の進行を「視力パンデミック」という視点で整理し、国内外の最新データをもとに原因や予防策を考えます。
 cortisちゃん
cortisちゃん「スマホの使いすぎが本当に近視を加速させているか、一緒に見てみよう!」
子どもの近視進行率(文科省/WHO等)
近年、世界的に子どもの近視有病率は急速に上昇しています。1990年の24.3%から2023年には35.8%まで増加し、2050年には約39.8%に達すると予測されています。国内でも、年齢とともに有病率が高まり、幼稚園児から高校生まで大きく進行していることが明らかです。
| 学齢 | 近視有病率 |
|---|---|
| 幼稚園 | 5.8% |
| 小学生 | 34.9% |
| 中学生 | 74.2% |
| 高校生 | 85.0% |
引用元:Jinghong Liang et al., Global prevalence, trend and projection of myopia in children and adolescents from 1990 to 2050 (British Journal of Ophthalmology, 2024)
引用元:Prevalence and risk factors of myopia among children and adolescents in China (Scientific Reports, 2024)
屋外活動とスマートフォン使用時間の関係
屋外での活動時間が多いほど近視リスクが低減し、一方でスマートフォンなどのスクリーン時間が増えるほど進行リスクが上昇します。
| 要因 | 近視リスク変化 |
|---|---|
| 屋外活動 ≥ 2時間/日 | −28% |
| スクリーンタイム +1時間/日 | +21% |
引用元:Epidemiology of Myopia (Wikipedia)
引用元:Seoul National University College of Medicine Study: One hour of screen time increases myopia risk by 21% (2025)
ブルーライトの影響に関する科学的知見
本節では、ブルーライトが目と睡眠に及ぼす影響について、主要な学術レビューと睡眠リズム研究の知見をまとめます。
 cortisちゃん
cortisちゃん「ブルーライトの真実、エビデンスと一緒にチェックしてみよう!」
学術的レビュー結果(日本眼科学会/コクラン)
コクランレビュー(2023年)では、市販のブルーライトフィルターレンズがコンピュータ使用による眼精疲労や視力保護、睡眠の質改善に対し統計的に有意な効果を示さないことが報告されました。17件のランダム化比較試験をメタアナリシスした結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 結果 |
|---|---|
| 眼精疲労軽減 | 有意差なし |
| 視力保護 | 有意差なし |
| 睡眠の質 | 有意差なし |
夜間のブルーライトと睡眠への影響
ハーバード大学の研究では、6.5時間の青色光曝露が緑色光と比較してメラトニン分泌を約2倍長く抑制し、概日リズムを約3時間遅延させることが示されています。
| 光の色 | メラトニン抑制時間 | 概日リズムの遅延 |
|---|---|---|
| 青色光 | 約6時間 | 約3時間 |
| 緑色光 | 約3時間 | 約1.5時間 |
引用元:Harvard Health: Blue light has a dark side
ドライアイの実態と主なリスク要因
本節では、日本におけるドライアイの有病率と主なリスク要因を解説します。
 cortisちゃん
cortisちゃん「目の潤いを守るには原因を知ることが第一歩だよ!」
画面作業者のドライアイ有病率(Osaka Study)
オフィスワーカーを対象とした「Importance of Tear Film Instability in Dry Eye Disease in Office Workers Using Visual Display Terminals: the Osaka Study」では、ドライアイ(確定または疑い)の有病率が男性60.1%、女性76.5%、全体で約65%と報告されています。
| 集団 | ドライアイ有病率 |
|---|---|
| 男性(VDT作業者) | 60.1% |
| 女性(VDT作業者) | 76.5% |
| 全体(VDT作業者) | 約65% |
画面作業時間・空調・女性ホルモンの影響
VDT使用時間の増加、オフィスの空調環境、女性ホルモンの変動はそれぞれドライアイリスクを高める要因です。
| リスク要因 | リスク倍率/影響 | 出典 |
|---|---|---|
| VDT使用 ≥8時間/日 | オッズ比 1.94 | Uchino M. et al., 2013 |
| エアコン長時間利用(湿度20%以下) | 涙液蒸発促進 | Osaka Study |
| 女性ホルモン(閉経後エストロゲン低下) | リスク増加 約1.7倍 | McMonnies et al., 2016 |
引用元: PubMed: 23891330 ; Bohrium:「Osaka Study」 ; PubMed: 27018682
眼鏡・コンタクトの使用率(年代別・男女差)
日本では長年、視力矯正の主流はメガネですが、コンタクトレンズも若年層を中心に根強い人気があります。最近は外見の自由度やスポーツ時の利便性から、両者をシーンによって使い分けるユーザーも増えてきました。
 cortisちゃん
cortisちゃんメガネは手軽で安全、コンタクトはアクティブな毎日にピッタリ。あなたのライフスタイルに合った選択が重要です!
眼鏡使用率の現状
最新の意識調査では、日本人の“日常的にメガネを使用している”割合が75.7%に達し、4人に3人が何らかの形でメガネをかけていることがわかりました。年代が上がるほど使用率は上昇し、老眼鏡のニーズ増加も背景にあります。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 日常的にメガネを使用(「常に」+「必要なときだけ」) | 75.7% |
| 男性:「常にかける」 | 40.8% |
| 女性:「常にかける」 | 22.8% |
引用元: プラネット『意識調査 Fromプラネット Vol.71』
コンタクト使用の傾向とリスク
成人の約18.5%、およそ2,350万人がコンタクトレンズを日常的に装用しています。一方、感染性角膜炎の全国調査では、10~20代の患者の約90%がコンタクトレンズ装用者であったと報告されており、適切なケアと定期的な受診が不可欠です。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| コンタクトレンズ装用者(日本全体) | 約18.5%(約2,350万人) |
| 10~20代の感染性角膜炎症例における装用率 | 約90% |
引用元: J‑CASTニュース「コンタクトレンズユーザー数」、 厚労科研報告「感染性角膜炎の全国調査結果」
高齢者に多い眼疾患(加齢黄斑変性・緑内障など)
本節では、高齢者に多くみられる主要な眼疾患を概観し、加齢性黄斑変性(AMD)や緑内障などの現状と課題に焦点を当てます。
 cortisちゃん
cortisちゃん年を重ねても大切な視力を守るために、まずはどんな疾患があるかを知ろう!
加齢黄斑変性(AMD)の将来予測と世界患者数
加齢性黄斑変性(AMD)は世界的に増加傾向にあり、2020年には約290万⼈の患者がいると推定されています。さらに2050年には約570万⼈に倍増すると予測されています。
| 年 | 患者数(推定) |
|---|---|
| 2020年 | 290万⼈ |
| 2050年 | 570万⼈ |
国内での失明原因ランキング
日本における失明原因の上位は緑内障、加齢性黄斑変性、糖尿病網膜症で、最新調査では緑内障が約30.3%で第1位を占めています。
| 原因 | 割合 |
|---|---|
| 緑内障 | 30.3% |
| 加齢性黄斑変性 | 27.0% |
| 糖尿病網膜症 | 9.7% |
デジタルデバイスと眼精疲労の関係
本節では、長時間のデジタルデバイス使用が眼精疲労を引き起こすメカニズムと、その予防策として広く推奨される“20-20-20ルール”についてご紹介します。
 cortisちゃん
cortisちゃんスマホやPCと上手につきあうには、正しい休憩方法を身につけるのが大事だよ!
1日5時間以上使用の影響
1日5時間以上のビジュアルディスプレイ端末(VDT)使用者は、ドライアイ診断リスクが有意に増加し、特に女性での有病率が高いことが報告されています。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 平均デバイス使用時間 | 9.7時間/日 |
| 眼精疲労(DES)有病率 (CVSスコア≥6) | 62.6% |
引用元:Digital Screen Use and Dry Eye: A Review
“20‑20‑20ルール”とその対策
「20-20-20ルール」を認知・実践している人はごく少数ですが、実践者は眼精疲労症状の緩和を実感しているという調査結果があります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| ルール認知率 | 13.1% |
| 実践者割合 | 8.8% |
引用元:Myth‑Busting the 20/20/20 Rule
まとめ|統計から読み解く「目を守る」ためにできること
本記事でご紹介した各種統計データから見えてきたのは、視力低下やドライアイ、眼疾患は誰にとっても決して他人事ではないということです。日々の生活習慣を見直し、適切なセルフケアと専門家のサポートを組み合わせることで、大切な「目」を守り、健康的な視界を保つことができます。
目の悩みは公式LINEでお気軽に相談
「視界がかすむ」「目が疲れやすい」などの気になる症状があれば、まずは無料の公式LINEで相談してください。専門カウンセラーがあなたの症状やライフスタイルに合わせたアドバイスを行い、セルフケア方法や受診のタイミングまで丁寧にサポートします。
ミエルラボ全国店舗で始める視力回復サポート
ミエルラボは全国展開する視力回復専門サロンです。最新のトレーニング機器と光学機器を用いたプログラムで、専門スタッフが一人ひとりに最適なケアを提供します。初回カウンセリングは無料、継続プランにはウェブ限定の特別価格をご用意しています。
cortisパーソナルジム監修!JR淵野辺駅近くにある視力回復サロンです♪